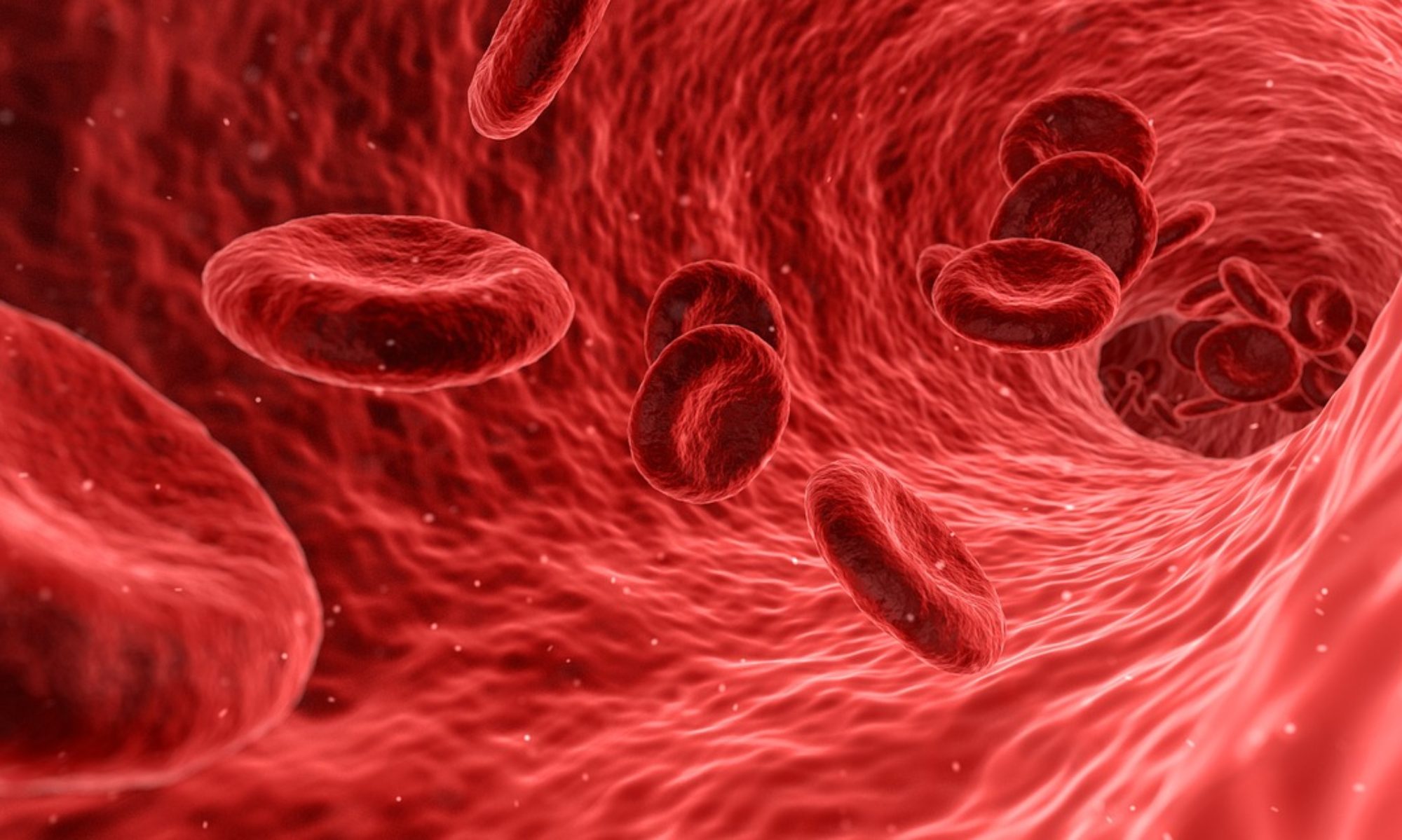サイトへようこそ。働く人が衛生的な環境で安全に働けることを目的とした任意団体です。組織向けには職長教育、労働災害防止の研修や講演活動を、個人向けには第一種衛生管理者試験の受験指導などを行っています。令和5年度は新型コロナ感染対策の緩和もあり、宮城での受験対策講習を再開いたします。他に栃木県那須塩原市、岩手県一関市(東磐職業訓練協会)の2カ所で定期開催を行っています。ご希望があれば各地で少人数での対面講習を行いますので、詳しくはお問い合わせください。
衛生管理者試験対策講習会はこちら
https://www.kokuchpro.com/group/eisei/
国家試験合格のコツ
人には長期記憶と短期記憶があります。例えば毎日見る新聞記事の内容などは、会社に出勤して話題にする間は覚えていますが、特に関心のないものは夕方には忘れていたりします。しかしその中でも悲惨な出来事や身近な出来事はずっと覚えていたりもします。
脳のメモリーは、防衛本能などと関連して、自分にとって重要なものや好むものだけを長期記憶に留めるよう、自動的にあらゆる情報をフィルターにかけているのです。
このことを裏返せば、「嫌々やる勉強が頭に入らない」「自分の仕事に関係ない勉強がうまくいかない」のは当たり前なのです。無意識のフィルターが働いているのですから、意識的に変えるのは難しいことです。
ではどうすれば良いでしょうか?一言で言えばその対策は、「好きになること」「関心を持つこと」なのですが、そうは言ってもそれができない、とお悩みの方は、以下のヒントを参考にしてください。
1:身近なものや状況に関連付ける
(衛生管理者の勉強は実は身近な事が多く含まれています)
2:教材を何度も変えない
(読みやすい教材を探し、それを使い続けることが関心を高めるコツです)
3:少しでもいいのでテキストや問題を毎日眺める
(寝る前や入浴時、休み時間、起きたときなど、時間を決めてルーティン化する)
4:わからない言葉がでてきたら放置せずその場で調べる
(ゆっくりでもいいので1つ1つ理解してから先に進んでください)*最初の通読は別
他にも、学習時や試験本番でのコツがたくさんあります。直接講習会ではトータルでご説明いたしますので、独学では難しいとお感じの方は、直接ご連絡いただくか、「こくちーずPRO」で告知している講習会にお申込みください。
◆テキストの直接販売を中止いたしました。
オリジナルのテキストは、東磐職業訓練協会(岩手県一関市)様、または講師が主催する直接講習でのみ使用することといたしました。職業訓練協会では年2回(2月頃と7月頃)の定期開催を行っていますので、ご興味のある方はお問い合わせください。
東磐職業訓練協会様
◆「第一種衛生管理者」国家試験 これまでの公表問題と解答はこちら(解答のみで解説はありません)
これ以前の公表過去問題も保持しておりますが、近年の大幅な法改正で、今では正解が変わっている問題も数多く出ています。あまり古い過去問をやるのはお勧めしません。直近3回分くらいをやってみて、すべての選択肢の根拠をテキストで確認していくやり方をお勧めしています。以下、念のため、平成30年以前の公表問題もそのまま掲載いたします。
◆採点しやすい過去問の解答用紙(印刷用)を用意しています。こちらからダウンロードしてお使いください。
◆直接講習会は令和5年現在、栃木県那須塩原市、千葉県市原市、宮城県仙台市のみで行っています。他に年2回、岩手県の東磐職業訓練協会の短期コースとして年2回、3日間コースで行っています。
自社講習は下記リンクをご参照ください。
https://www.kokuchpro.com/group/eisei/